|
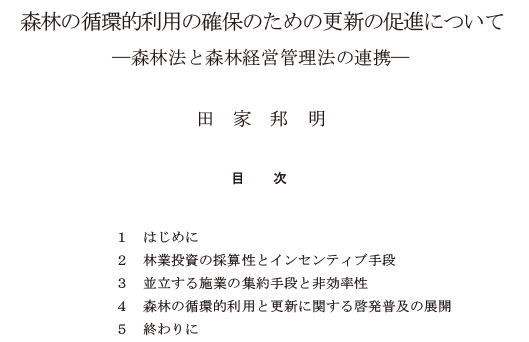 日本農業研究所田家理事長から、「森林の循環的利用の確保のための更新の促進について―森林法と森林経営管理法の連携―」という論文が公開されたと紹介を受けました。 日本農業研究所田家理事長から、「森林の循環的利用の確保のための更新の促進について―森林法と森林経営管理法の連携―」という論文が公開されたと紹介を受けました。
日本農業研究所研究報告『農業研究』第37号(2024年12月):田家邦明:森林の循環的利用の確保のための更新の促進について―森林法と森林経営管理法の連携―
40ページに及ぶ大論文ですべて読み切れていないのですが、最近の森林政策の動きを森林法と森林経営管理法の連携がとれていない!と批判的な評価をされていて、具体的な提言をされています。
提言内容などをご覧になって、「そうだそうだ!」「そうかも」、と思われるかたは、読んで頂いたらよいのでないか!と、このページで、「はじめに」部分に記載されている内容を中心に概要紹介します。
(全体の構成)
目次
1 はじめに
2 林業投資の採算性とインセンティブ手段
3 並立する施業の集約手段と非効率性
4 森林の循環的利用と更新に関する啓発普及の展開
5 終わりに |
上記が目次です。はじめにの部分に全体概要が記載されているので、これを中心に紹介しますが、第2節以下の概要は・・・
第2節
保続のための適正な林齢での主伐、適正な伐採立木材積による森林経営を促すための政策手段の要であるインセンティブ措置が、意向調査に現われているように造林投資に関し採算性がとれないと認識されているように、効果が乏しくなっていることが主伐の意欲を減殺していることを説明。
さらに、林野当局は、施業の集約によって素材生産業者等に生じるメリットが、立木価格に還元されることを期待する戦略を進めているが、これは市場における双方の交渉によるものであるため実現する保証がないことを指摘。
第3節
森林経営管理法による経営管理実施権の配分は、素材生産業者等が供給サービスについての市場(プラットフォーム)を細分化し、しかも需要者の委託料の支払用意は小さく、魅力に乏しいものとなって、施業の集約をかえって妨げる可能性があることを明らかに。
経営管理実施権の配分に代えて、参加者が限定されないマッチングの場にあっせんし、同法は市町村が自ら森林整備を行なうための経営管理権に関するものに限定し、施業の集積方法は森林法の森林経営計画に一元化することが適当であることを指摘。
第4節
消費者の便益には、森林の循環的利用がもたらす公益的機能に貢献することの効用が含まれており、インセンティブ措置の効果を高めるため、啓発努力を行なう必要性とそれが効果を持つために森林法やそれに基づく森林計画等に位置付けることが有効であることを説明
第5節:しめくくり
(具体的提言の内容)
提言1:森林法の見直し
・森林法の全国森林計画、地域森林計画及び市町村森林整備計画に、森林の循環利用のため更新の促進を計画事項とする。市町村森林整備計画においては更新を行なうべき森林区域を指定することとし、地域森林計画にその設定方法を規定する。
・伐採跡地造林が4割程度に止まっているため、造林命令を発出できることとし、最近の降雨状況から、間伐未実施林以上に、土砂崩れ等の要因となるおそれが格段に大きいので、造林命令に従わない場合に罰則を設ける(そのためにも、全国森林計画等に森林の循環的利用のための更新の促進を明定する必要がある)
提言2:森林経営管理法の見直し
・森林経営管理法において、自ら森林の管理経営を行なう意思がない森林所有者で施業の委託サービスの購買意向を有する者と委託サービスを提供する者(素材生産業者等)の取引を行なうプラットフォームを開設(運営費用は、森林環境税を充てる)
・指定法人が指定された場合は、市町村が経営管理権を取得して自ら森林整備を行なうも場合を除き、経営管理権は設定しない。
・森林所有者から委託サービスの購入について意向が示された森林については、指定法人における取引についてあっ旋が行なわれるようにする。
・森林経営管理法に関連なく、森林法の森林経営計画の関係者間の協議等の準
備において、市町村、県、関係団体等は、施業の集積に当って、指定法人の
プラットフォームを活用するようにし、取引の参加者を増加させる。
・指定法人は、市町村に代って、経営管理権に係る事務事業を実施できるよう
にする。
・これらの見直しを通じて、新たな森林管理システムは、森林環境譲与税の使途として期待されている市町村が森林所有者に代わり森林整備を行うという森林の有する公益的機能の発揮(公共財の供給)を主力において運用することとし、個々の森林所有者の経営管理の状況、森林所有者の意向調査、所在地が不明の森林所有者の探索、自ら行う森林整備事業の手続き等を行うことに重点化する。素材生産業者等に経営管理を再委託する部分は市町村への委託を行うことなく、森林組合等と直接繋げるようにあっせんを行う方法に転換し、施業の集積手段を森林法の森林経営計画に一元化する。
提言3森林法に基づくインセンティブ措置の見直し
・50年後の立木販売収入(現在割引価値)に対する再造林や育林経費(現在割引価値)の実質的負担は、販売収入の割引による減価に比べ、費用のほとんどは10年以内に要するため割引による減価が小さいことから大きくなる。それが主伐に対するインセンティブ効果をより減殺している可能性がある。このため、主伐に近い時点に限って、査定係数を引き上げるとともに、県、市町村の嵩上げの制度化を要請する(森林林業基本法第6条の援用等)。
・森林経営計画の策定が難しい森林について、更新を確保するため、要件を緩和するとともに、査定率を下げて補助金の対象とする。
提言4森林の循環的利用(将来の緑と水の源泉、森林吸収源)の確保のための更新(伐採と再造林の確保)の大切さを訴求する運動の展開
・ 森林所有者の森林に対する投資は、経済的な利益だけでなく、将来の緑と水,森林吸収源に対する貢献による満足感という効用を織り込んで意思決定されるようにする。
・伐採跡地の未造林は、地域の社会規範の緩みやそれに縛られない不在村所有者の増加も影響している可能性があるので、県の森林環境税や国の森林環境譲与税を活用した啓発普及事業を使い、戦後の植林運動に倣って、若返りのための植林の大切さ訴える
ーーーー以上
 是非をご覧ください 是非をご覧ください
:日本農業研究所研究報告『農業研究』第37号(2024年12月):田家邦明:森林の循環的利用の確保のための更新の促進について―森林法と森林経営管理法の連携―
ーーーー
なお、森林経営管理法、森林法の改正案が閣議決定して、4月に審議入りだそうです。(内容は、この論文とすれ違いですが)
林野庁:森林経営管理法等の見直しの 検討状況について
林政ニュース森林経営管理法・森林法改正案を閣議決定、審議入りは4月中旬以降
kokunai6-71<taie_renkei>
|

